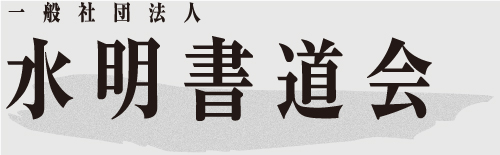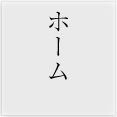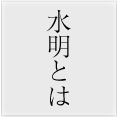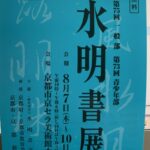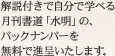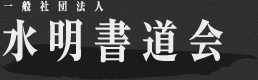「うたごよみ」によせて その2「梅」
「松」「竹」、その次はやはり「梅」でした。予想通りでしたね。
梅は、春の到来を象徴する花として、古来より愛されてきました。
ちょうど、水明誌2月号の「条幅研究 かな部」のA課題が、
「大空は梅のにほひに霞みつつ曇りも果てぬ春の夜の月」
で藤原定家の歌でした。
この歌のかな創作では、「にほひ」の連綿表現に苦労されたのでは、と思います。歌の意味としても「にほひ」がキーポイントのようです。
そして、冷泉家のホームページの「文庫がたり・やまと歌がたり 第四歌」にもあるように、この歌も「素晴らしい大嘘?のお話の歌」かな、と感じます。
「大空」が「梅の香り」で霞むかな?と疑問ですね(笑)。

この歌は、新古今和歌集 巻1春歌上にあり、同じ新古今和歌集の大江千里の下記の歌を本歌としています。
「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」
(大意:さわやかに照るのでもなく、といって全く曇ってしまうのでもない、春の夜のおぼろにかすむ月の美しさに及ぶものはない)
大江千里の歌は、視覚だけでとらえていますが、藤原定家の方は、「にほひ」を詠みこんで臭覚を加味しています。この「梅のにほひ」を取り合わせることによって、よりあでやかで美しい夜を演出することに成功しています。

「梅の香り」には、「香を焚きしめた異性」を想うという「恋こごろ」を歌っているとも考えられるようです。恋を連想することにより、梅の香りがより魅力的なものになる訳です。
現在、掲載中の「臨書講座かな」の「関戸本古今集」は、古今集を書写したものです。その中に次の歌があり、筆致もすばらしいですが、歌の内容も実に艶やかです。
春の夜の やみはあやなし 梅の花 色こそ見えね かやはかくるる
(古今・春上・四一・凡河内躬恒)
【現代語訳】(闇とはあらゆるものをすっぽりと隠すものだが)春の夜の闇はどうも筋の通らないことをしている。梅の花の、色こそ見えはしないが、その香は隠すことはできないから。
春の夜の闇に漂う梅の香りを着物に香をたきしめた女性に見立てていて、上品さが光る一首です。
京都には、梅の名所がたくさんあります。私のおすすめは、北野天満宮はもちろんですが、京都御苑(御所)の梅園です。無料ですので、何度も訪れられます。
平日に行くと幼稚園の園児が遊んでいて、心和む光景です。
その他、小さなお寺や神社の境内、民家の庭先で梅を見ると、春が来たなあと嬉しくなります。
今年の梅は、二月の寒気が影響して遅いようですが、色々な和歌を思い出しながら、梅を観賞し楽しんでみてください。

さて、最後に。花より団子派の私としては、虎屋の羊羹の「夜の梅」を思い出します。
この羊羹も実に風流で上品。 羊羹の切り口にのぞく小豆を、夜の闇の中で咲く梅の花に見立てて命名されたそう。さてさて、この梅は、白梅か紅梅のどちらでしょう?
2025年3月 編集部 北川詩雪